2025/11/09
お知らせ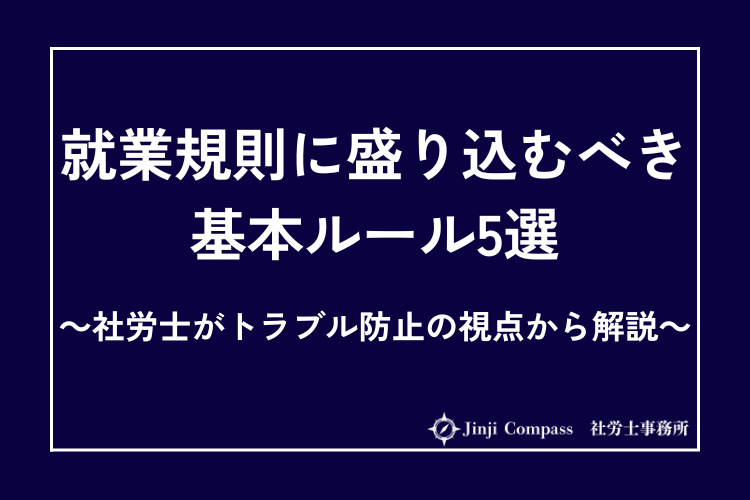
埼玉県さいたま市を中心に、埼玉県内やWebを通じて
全国の中小企業の就業規則の作成・改定を支援するJinji Compass 社労士事務所です。
「作ったけれど使っていない」「トラブルが起きてから慌てて開く」——現場ではこうした声をよく聞きます。
就業規則は、会社と従業員が安心して働くための共通ルールであり、労務トラブルを未然に防ぐ盾です。
ただし、内容が曖昧だったり実態とズレていると、逆に紛争の火種にもなり得ます。
近年は、SNS・副業・ハラスメント・メンタル不調・育児介護など、従来のテンプレートでは捉えにくいテーマが増えています。
「うちは小さい会社だから」と後回しにすると、いざという時に会社を守る根拠が無い状態になりかねません。
就業規則は“提出書類”ではなく、経営リスクを管理する実務ツールです。
本記事では、全国の中小企業を支援する中で得た実務経験をもとに、
Jinji Compass 社労士事務所が実務で重視するトラブル防止の必須5条項を、分かりやすく解説します。
就業規則は、作れば安心ではありません。法的要件を満たしていても、現場の運用と噛み合わなければ効力が出ないことが多々あります。
いずれも“形だけの規程”の典型です。
重要なのは、次の3点を同時に満たすこと。
とりわけ副業やSNSのように法令条文に直接現れにくい領域は、会社の判断方針を明文化しておくことが欠かせません。
裁判・行政対応の現場では「就業規則が実態を反映していないため懲戒が無効」になる例が少なくありません。
つまり、就業規則の整備=会社防衛の土台づくりです。
実務でよくある事例:
根本原因の多くは、事前にルールを明文化していないこと。
Jinji Compass 社労士事務所は、法令準拠はもちろん、理念や業種特性(医療・IT・建設など)を反映し、
「守るためのルール」から「成長を支えるルール」へ進化させる設計を重視します。
本記事(前編)は、就業規則の整備・改定で「まず押さえるべき基本ルール5項目」を、社労士の実務目線で解説します。
各項目で、起きやすいトラブル → ルール化の要点 → 運用のコツの順に整理しています。
※後編では、育児・介護休業、賃金・手当、ハラスメント防止、安全衛生、届出・運用など、制度面を深掘りします。
▶ 後編はコチラ: 就業規則に盛り込むべき制度・運用ルール5選|社労士が“機能する仕組み”を解説
懲戒や服務規律の条文は、就業規則の中でも最もトラブルが発生しやすい分野です。
実際に「懲戒処分を行ったのに、就業規則上の根拠がなく無効とされた」
というケースも珍しくありません。
懲戒は会社にとって“最終手段”であり、慎重な手続と公平な判断が求められます。
たとえば、遅刻・無断欠勤・業務命令違反・会社の信用を損なう行為などは、
多くの企業で懲戒事由として定められています。
近年では、SNSでの不適切な投稿や情報漏洩など、
従来の就業規則では想定されていなかった行為も問題化しています。
一度の発信でも企業の信用を損ねるおそれがあり、社会的な影響は大きくなっています。
こうしたリスクを防ぐためには、懲戒条項を「種類」「事由」「手続」の
3つの柱で整理しておくことが重要です。
懲戒の種類は、行為の内容や情状に応じて段階的に設けておきます。
条文には「情状に応じてこれらの処分を行うことがある」と記載しておくと、
柔軟な判断が可能です。
種類を明確にしておくことで、処分の重さに一貫性が生まれます。
懲戒対象となる行為を、具体的かつ網羅的に列挙しておくことが大切です。
また、「その他前各号に準ずる行為で会社が懲戒の必要があると認める場合」といった
包括条項を加えると、想定外の行為にも対応できます。
懲戒は内容よりも手続の正確さで無効とされるケースが多い分野です。
以下の3点は必ず明記しておきましょう。
こうしたプロセスを整えておくことで、公平性が担保され
「不当懲戒」とされるリスクを防げます。
懲戒条項の目的は、社員を処分することではなく、職場秩序を保ち再発を防ぐことにあります。
「種類」「事由」「手続」を整備しておくことで、会社の判断に一貫性が生まれ、
社員にも安心感を与えます。
懲戒規定は、“厳罰化”のためではなく、
会社と社員の信頼関係を守るルールづくりとして整えることが理想です。
近年は働き方改革の影響もあり、副業・兼業を認める企業が増えています。
厚生労働省もガイドライン(副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説)の中で「原則として副業を認める方向」を示していますが、
実際の現場では「どこまで許されるのか」「どのようにルールを設けるべきか」といった相談が後を絶ちません。
副業は、社員のスキル向上やモチベーションアップにつながる一方で、
競業行為・情報漏洩・労働時間の管理といったリスクも伴います。
「自由」を認めながらも、会社の秩序と安全を保つためには、
就業規則上での明確なルールづくりが欠かせません。
副業を一律禁止とすると、労働者の自由を過度に制限するおそれがあります。
そのため、実務上は「届出制」または「承認制」を採用する企業が増えています。
このように定めておくことで、
会社として把握・管理ができる状態を維持しながら、柔軟に対応できます。
副業を制限する場合は、禁止の理由を具体的に明示することが重要です。
たとえば、以下のような行為は制限対象とするのが一般的です。
このように「禁止の範囲」を合理的に定義しておくことで、
社員にとっても納得感のあるルールになります。
副業を認める際には、労働時間の通算にも注意が必要です。
労働基準法では、複数の会社で働く場合でも「1日の労働時間の合計が8時間以内」となるよう調整が求められます。超過した分は割増賃金の対象になります。
つまり、会社が副業を黙認している場合でも、過重労働が発生すれば安全配慮義務違反に問われるリスクがあります。
また、情報漏洩防止や競業防止の観点から、
秘密保持義務や情報管理規程との整合性を図ることも重要です。
副業のルールは単独ではなく、就業規則全体とのバランスの中で整備する必要があります。
副業・兼業制度は、社員にとっても企業にとっても“使い方次第”の制度です。
一律に禁止するのではなく、届出制や条件付き承認によって、
柔軟に認めながら会社の信用と秩序を守る仕組みに整えることが理想です。
副業に関するルールは、“制限のための規定”ではなく、
安心して本業にも集中できる環境をつくるためのルールとして設計することが、
これからの時代の労務管理に求められる考え方です。
SNSやオンライン発信が当たり前となった今、
「従業員の何気ない投稿がトラブルに発展した」という相談が増えています。
以前は社外に出ることのなかった社内情報や人間関係が、
スマートフォン一つで一瞬にして拡散される時代です。
投稿した本人に悪意がなくても、会社名や顧客名、職場の写真などが含まれていれば、
企業の信用を損なう可能性があります。
中には、口コミサイトや匿名掲示板の書き込みから取引先との関係が悪化したり、
採用活動に影響が出たケースも見られます。
こうしたリスクを防ぐためには、就業規則の中でSNS利用や情報管理のルールを明文化しておくことが欠かせません。
まず、従業員が取り扱う情報のうち「社外に出してはならない範囲」を明確にしておきます。
「どこからが秘密情報なのか」があいまいなままだと、本人も判断できません。
規程で具体例を示しておくことで、従業員が安心して情報を扱えるようになります。
SNSに関するルールは、禁止だけでなく判断基準を示すことが大切です。
たとえば、就業規則に次のような内容を盛り込みます。
単なる「SNS禁止」ではなく、何をどう使えば問題になるのかを可視化することがポイントです。
社員の意識を高めつつ、会社としての姿勢を明確に示す効果があります。
就業規則に定めるだけでなく、社内周知と教育も重要です。
入社時研修や定期的なミーティングで、SNSの注意点や実例を共有しておくと、
従業員の「知らなかった」を防げます。
また、社内でトラブルが発覚した際には、
削除指導・再発防止・懲戒判断などのフローを定めておくと、迅速に対応できます。
「発信ルール」を整えることは、社員の表現を制限するものではなく、
会社と社員の双方を守るためのリスクマネジメントです。
SNSが当たり前の今、会社の情報は簡単に社外へ広がります。
だからこそ、情報管理と発信ルールは「信頼を守る仕組み」として位置づけることが重要です。
就業規則に明文化し、教育と運用をセットで行うことで、
トラブルを防ぎつつ、社員が安心して発信できる環境を整えることができます。
ルールは縛るためではなく、信頼を守るためにある——それがSNS時代の労務管理の基本です。
ここ数年で急増している相談のひとつが、「メンタル不調による長期欠勤や休職への対応」です。
社員の体調や心身のバランスを崩すケースは決して珍しくなく、
特に少人数の事業所では、1人が休職するだけで業務が滞ってしまうこともあります。
このようなトラブルを防ぐためには、就業規則の中で休職と復職のルールを明確にしておくことが欠かせません。
「どんな状態で休職になるのか」「どのくらいの期間認めるのか」「復職はどう判断するのか」を定めておくことで、
会社も社員も安心して対応できる体制を整えられます。
休職とは、社員が病気やけがなどで長期に働けなくなった場合に、
一定期間、雇用関係を保ったまま就労義務を免除する制度です。
一般的な構成としては、次のような要素を就業規則に記載します。
このように条件を明確にしておくことで、「休職に該当するのか」「退職扱いになるのか」といった
あいまいな判断を避けることができます。
復職の可否は、本人の希望だけでなく、業務遂行が可能な状態かどうかで判断します。
そのため、就業規則には「主治医または産業医の意見を参考に会社が判断する」と記載しておくとよいでしょう。
また、最近では「段階的な復職制度」を設ける企業も増えています。
たとえば、復職直後の一定期間を短時間勤務にしたり、
試し出勤(リハビリ出勤)として様子を見る仕組みを導入するなど、
無理のない形での職場復帰をサポートする考え方です。
これらの制度を就業規則に反映させておくことで、
再発防止と早期定着の両立が可能になります。
休職制度を形だけ定めても、実際に運用できなければ意味がありません。
制度を活かすためには、次の3点を意識することが重要です。
また、休職期間満了後に回復しない場合の取扱い(退職扱いとする等)も明確にしておくことで、
後々のトラブルを防ぐことができます。
休職・復職の制度は、会社を守るだけでなく、社員を支えるためのルールでもあります。
あいまいな運用では、かえって不信感や誤解を生むおそれがあります。
就業規則に明確な基準を設け、復職の流れを整えることで、
社員が安心して治療に専念でき、職場も安定して運営できます。
「備えあれば憂いなし」——休職制度はリスク管理と信頼構築の両輪です。
有給休暇や特別休暇のルールは、会社と社員双方にとって身近なテーマです。
しかし、実務の現場では「申請方法が決まっていない」「上司によって対応が違う」といった声が少なくありません。
就業規則上で明確にしておかなければ、
“誰に・いつ・どんな条件で休みが認められるのか”が曖昧になり、トラブルの原因となります。
休暇制度を「使える制度」として運用するには、
法律の基準に加えて、自社の実態に合った運用ルールを整備することが大切です。
有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利です。
その一方で、会社には業務運営上の調整権(時季変更権)も認められています。
両者のバランスを取るためには、取得の手続や期限を明確にしておくことが欠かせません。
たとえば、就業規則には以下のような項目を定めておくと安心です。
これらを明文化することで、社員の申請や管理者の判断が統一され、
「人によって対応が違う」という不公平感を防げます。
法定外の休暇である「特別休暇」は、
企業文化や福利厚生の一環として設けることで、社員の満足度や定着率を高める効果があります。
代表的なものとしては次のような休暇があります。
特別休暇は法定義務ではありませんが、
「社員を大切にする姿勢」を伝える企業メッセージにもなります。
また、制度内容を明確にしておけば、助成金(例:働き方改革推進支援助成金)の対象となる場合もあります。
制度を設けても、実際に社員が利用できなければ意味がありません。
有給・特別休暇を“使える制度”にするためには、次の3つの視点が重要です。
特に「管理者が制度を理解していない」ことが、現場のトラブルを招く大きな要因です。
制度の周知と教育を同時に行うことで、運用の質が格段に上がります。
休暇制度は、法律を守るための仕組みではなく、
社員が安心して働ける環境を整えるためのルールです。
明確な手続と柔軟な運用を両立させることで、
有給も特別休暇も「実際に使われる制度」へと変わります。
“休める会社”は、“続けられる会社”。
休暇制度の整備は、会社と社員の双方にとっての投資です。
前編では、トラブルを招きやすい基本領域を中心に、
「条文化の要点と運用の勘所」を整理しました。
ポイントは、法令×自社運用×トラブル想定の三位一体設計と、
現場で迷わない運用導線を整えることです。
ここまで整えることで、就業規則は“置いてある書類”から、
会社を守り、働きやすさを支える経営インフラへと進化します。
Jinji Compass 社労士事務所では、
小規模事業者でも導入しやすい段階的な就業規則整備をサポートしています。
「うちの会社ではどんな規程が必要?」「現行ルールにリスクは?」
そんな疑問があれば、まずはお気軽にご相談ください。
次の後編では、制度や運用の仕組みに焦点を当て、
以下のテーマを社労士の実務目線で詳しく解説します。
就業規則の整備は、「会社を守る」だけでなく、
社員が安心して働ける職場をつくるための投資です。
ルールの整備が、信頼関係の基盤をつくり、企業の成長を支える。
その実感を、後編で一緒に掘り下げていきましょう。
▶ 後編: 就業規則に盛り込むべき制度・運用ルール5選|社労士が“機能する仕組み”を解説
▶ 関連記事:
・就業規則が必要な会社と不要な会社の違いを社労士が解説~10人未満でも作成すべき理由~
・就業規則とは?会社に義務づけられる理由を社労士が解説