2025/11/09
お知らせ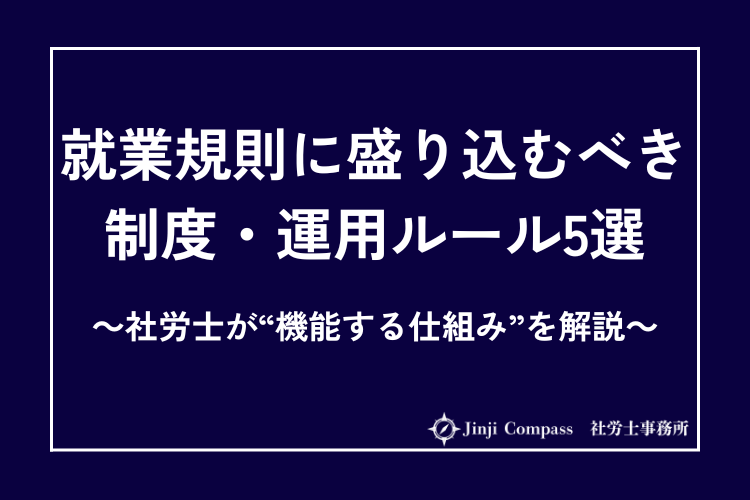
前編(就業規則に盛り込むべき基本ルール5選|社労士がトラブル防止の視点から解説)では、
懲戒・副業・SNS・休職・有給休暇の5分野を中心に、
「トラブルを防ぐためのルールづくり」を解説しました。
今回の後編では、より制度的・運用的な視点から、
育児・介護休業制度/労働時間・残業管理/賃金・評価制度/ハラスメント防止/退職・解雇手続き
という“会社運営の根幹”に関わる領域を取り上げます。
埼玉県さいたま市を拠点に、埼玉県内やWebを通じて全国の中小企業を支援する
Jinji Compass 社労士事務所では、就業規則を“書類”ではなく、
現場で活かせる「経営インフラ」として設計することを重視しています。
制度を整備することはゴールではなくスタートです。
「法令遵守 × 実態反映 × 運用可能性」の三拍子がそろってこそ、
会社を守り、社員が安心して働ける職場環境が実現します。
近年の法改正により、育児・介護休業制度は企業規模を問わず整備が求められるようになりました。
特に2025年10月改正では、柔軟な働き方を実現するための措置が新たに義務化され、
小規模企業でも制度の見直しが急務となっています。
2025年の改正についてはこちらからご確認ください。
▶厚生労働省|育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
しかし、実務の現場では「制度はあるけれど運用されていない」「周知が不十分」といった課題が多く見られます。
就業規則に正しく反映し、従業員が安心して取得できる環境を整えることが重要です。
育児休業制度は、育児・介護休業法に基づき、
原則として子が1歳に達するまでの間に取得できる休業制度です。
近年は、分割取得や出生時育児休業(いわゆる“産後パパ育休”)など、制度が多様化しています。
就業規則で明記しておくべき主なポイントは次のとおりです。
制度内容を曖昧にしたままでは、「会社として認める範囲」が不明確になり、
かえって取得しづらい雰囲気を生みかねません。
介護休業も同じく育児・介護休業法に基づく制度で、
要介護状態にある家族を介護するために休業できる仕組みです。
こちらも、次のような要件を就業規則に明記しておきます。
育児・介護の両制度は、どちらか一方のみ整備している会社もありますが、
「介護だけ」「育児だけ」では法対応が不十分となるため、セットでの整備が望まれます。
制度整備を進める際は、厚生労働省の助成金を活用することで負担を軽減できます。
代表的なものは次のとおりです。
これらの助成金はいずれも、就業規則等に制度を明記していることが支給要件の一つとなります。
つまり、「規定を整えること」がそのまま助成金の申請準備にもつながるのです。
育児・介護休業制度は、単なる法令対応ではなく、
社員のライフイベントを支えるための仕組みです。
就業規則に明確な条文を設け、制度を正しく運用することで、
社員が安心して働き続けられる職場づくりが実現します。
助成金を活用しながら制度を整備すれば、
企業にとっても「人を大切にする会社」としての信頼を高めるきっかけになります。
“法対応”から“人材戦略”へ——それが今求められる制度設計の方向性です。
労働時間の管理は、どの会社でも避けて通れない重要テーマです。
しかし、実務では「タイムカードを押してから残業」「自己申告が形だけ」といった、
“形骸化した運用”が問題になるケースが少なくありません。
労働時間の管理を誤ると、未払い残業代や過重労働による労災など、
会社にとって大きなリスクにつながります。
就業規則には、法令を満たすだけでなく、
実際の働き方に即したルールを定めることが求められます。
労働基準法では、原則的に1日8時間・週40時間が法定労働時間と定められています。
これを超えて勤務させる場合には、いわゆる「36協定(時間外・休日労働協定)」の締結と届出が必要です。
就業規則には、次のような基本項目を明確にしておきましょう。
実態と合わない定め方をすると、“規定上は守っているが現場では違う”というギャップが生まれ、
是正勧告やトラブルの原因になります。
残業(時間外労働)は、原則として会社の指示・命令によって行うものです。
「社員が自発的に残っていた」「上司は知らなかった」という説明では、
実務上は“黙認”とみなされ、残業代の支払い義務を免れません。
そのため、就業規則には以下のようなルールを定めておくことが重要です。
こうした条文を明記しておくことで、「必要な残業」と「不必要な残業」の線引きを明確にできます。
勤怠管理の目的は、単に労働時間を把握することではなく、
過重労働を防ぎ、安全を守ることにあります。
形式的な打刻や、サービス残業を前提とした運用を放置すると、
「長時間労働を容認していた」と見なされるおそれがあります。
次のような運用を行うことで、労務リスクを大きく減らせます。
また、固定残業手当を導入している場合は、
想定時間を超える残業には追加支給が必要である点にも注意が必要です。
労働時間のルールは、法令で定められた最低限の基準に過ぎません。
本当に重要なのは、自社の働き方に合わせて現場で運用できる形に落とし込むことです。
“書いてあるだけ”の就業規則ではなく、
“現場で守れるルール”として整備することが、トラブル防止と社員の安心につながります。
就業規則は、形ではなく運用。
そこに経営の本気度が表れます。
給与や賞与のルールは、社員のモチベーションに直結する重要なテーマです。
しかし、就業規則や賃金規程の整備が不十分なまま運用していると、
「昇給の基準がわからない」「賞与が支給されなかった」などの不満が生じ、
労務トラブルの原因になることがあります。
賃金・賞与・評価制度は、会社の“経営方針を映す鏡”です。
制度を整備することで、公平な運用と社員の納得感を両立できます。
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業場において、
就業規則を作成し、届け出ることが義務づけられています。
就業規則には必ず記載しなければならない、絶対的必要記載事項があり、
その中では「賃金の決定・計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」が定められています。
まずは、賃金規程に次のような内容を明記しておくことが基本です。
特に固定残業手当を導入している場合は、
「何時間分の残業を含むのか」「超過分の支払い方法」を明確にしておくことが不可欠です。
不明確なまま運用すると、未払い残業のリスクが高まります。
賞与は原則として会社の裁量により支給される任意の制度ですが、
就業規則や過去の慣行が“支給の約束”とみなされることがあります。
たとえば、「毎年○月に支給する」と明記していたり、
長年同時期に支給を続けていた場合には、
「当然もらえる権利がある」と判断される可能性があります。
そのため、就業規則には次のような表現を用いるのが安全です。
「賞与は業績および勤務成績を考慮し、会社の裁量により支給を決定する」
また、支給対象期間や在籍要件(例:支給日に在籍している社員に限る)を
明記しておくことで、退職前後のトラブルも防げます。
評価制度は、昇給や賞与の根拠となる仕組みです。
基準が不明確だと、「上司の好き嫌いで決まっている」「何を頑張れば評価されるのか分からない」といった不満が生まれます。
実務的には、次の3点を整備しておくと運用が安定します。
評価は“査定”ではなく、“成長支援”の仕組みとして運用することが大切です。
社員が自分の課題を理解し、努力の方向性を共有できるようになります。
賃金・賞与・評価に関するトラブルは、ほとんどが「説明できない」「書いていない」ことから起こります。
金銭に関する規定こそ、感情ではなくルールで公平に扱うことが重要です。
明確な賃金規程と評価制度を整えることで、
社員は安心して働け、会社もリスクを防ぐことができます。
“曖昧さ”をなくすことが、信頼を守る最大の防御策です。
パワハラ・セクハラ・マタハラなど、職場でのハラスメントをめぐる問題は年々増加しています。
厚生労働省の「改正労働施策総合推進法」により、
2022年4月から中小企業にもハラスメント防止措置が義務化され、
すべての企業が対応を求められる時代になりました。
しかし、実際の現場では「相談窓口は設置したが、運用できていない」「何がハラスメントに当たるのか分からない」
といった声も多く聞かれます。
就業規則に明確な防止条項を設け、運用ルールを整備することが、
トラブルを未然に防ぐ第一歩です。
ハラスメント防止の取組みは、単なる努力義務ではなく、企業の法的義務です。
改正法では、すべての事業主に次の3つの措置が求められています。
これらを就業規則に反映させ、誰もが分かる形で明文化しておくことが重要です。
ハラスメント防止に関する条文は、
“禁止”と“対応手続”の2つの観点から整理するとわかりやすくなります。
禁止内容の例
対応手続の例
こうした条文を入れておくことで、“会社としてどこまで対応するか”が明確になります。
ハラスメント防止条項は、書いただけでは機能しません。
実際に効果を発揮するためには、次のような仕組みづくりが必要です。
また、外部相談窓口(社労士・弁護士等)と連携しておくことで、
公正性を保ちながら適切な対応が可能になります。
ハラスメント防止は、法律で義務づけられたから行うものではなく、
社員が安心して働ける職場文化をつくる取り組みです。
就業規則に明確な条文を設け、実際に運用できる体制を整えることで、
トラブルを防ぎ、社内の信頼関係を守ることができます。
ハラスメント対策は、「守りのコンプライアンス」から「攻めの職場づくり」へ。
その意識の変化こそが、健全な組織の第一歩です。
社員の退職や解雇は、会社にとって避けて通れない局面です。
どんなに良好な職場であっても、「退職のタイミング」「引継ぎ」「解雇の是非」をめぐって
トラブルに発展するケースは少なくありません。
就業規則に明確な手続きと基準を定めておくことは、
会社と社員の双方を守る“最終防衛線”です。
まず、一般的な退職(自己都合退職)については、民法第627条で
「期間の定めのない雇用は、退職の申出から2週間を経過すれば終了する」と定められています。
しかし、現実の業務では引継ぎや人員調整の必要があるため、
就業規則では次のようなルールを定めておくと安心です。
これにより、「突然辞めたいと言われて困った」「引継ぎが終わらないまま退職した」といった
実務上のトラブルを防ぐことができます。
解雇は、会社側の判断で雇用関係を終了させる最も重い処分です。
そのため、法的にも非常に厳しく制限されています。
労働契約法第16条では「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当でなければ無効」とされています。
解雇を行う際には、次の3点を必ず守ることが必要です。
これらが不十分なまま解雇すると、「不当解雇」と判断されるリスクが高くなります。
就業規則の中では、「懲戒解雇」「普通解雇」「整理解雇」などを区別し、
それぞれの根拠と手続を明確にしておくことが大切です。
長期休職後に回復が見込めない場合など、
「自然退職(休職期間満了による退職)」として扱うケースもあります。
この場合も、実態としては「解雇」と同様の法的性質を持つため、慎重な運用が求められます。
あくまで「一方的な終了」ではなく、一定の手続を経たうえでの退職と位置づけることが重要です。
退職・解雇のトラブルは、手続を曖昧にしたことから生じるケースが大半です。
退職を希望する社員にも、解雇を判断する会社にも、
共通のルールがあることで無用な誤解を防ぐことができます。
退職は終わりではなく、企業としての“信頼が試される場面”。
ルールを整備し、丁寧に対応することが、
結果的に会社の評価と安心を守る最善の防御策です。
制度やルールは、社員を縛るためのものではなく、
会社と社員の信頼を可視化する仕組みです。
就業規則に正しく制度を落とし込み、現場で運用できる形に整えることで、
トラブルを未然に防ぎながら、社員が安心して働ける職場を実現できます。
本記事で取り上げた5つの制度――
育児・介護休業、労働時間、賃金・評価、ハラスメント防止、退職・解雇。
これらはいずれも“会社を守りながら人を活かす”ための柱です。
Jinji Compass 社労士事務所では、
中小企業の実態に合わせた制度設計・規程改定をサポートしています。
法改正対応はもちろん、運用面のフォローや助成金活用まで一貫して支援し、
「制度を整えることが経営の安心につながる」ことを実感いただける体制を整えています。
就業規則は、作って終わりではなく、育てていくもの。
“制度が活きる職場づくり”を、私たちと一緒に進めていきましょう。
▶ 前編: 就業規則に盛り込むべき基本ルール5選|社労士がトラブル防止の視点から解説
▶ 関連記事:
就業規則が必要な会社と不要な会社の違いを社労士が解説~10人未満でも作成すべき理由~
就業規則とは?会社に義務づけられる理由を社労士が解説